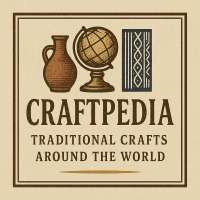有田焼
概要
有田焼(ありたやき)は、17世紀初頭に九州の佐賀県有田町で誕生した、日本を代表する磁器です。洗練された美しさ、繊細な絵付け、そして世界的な影響力で知られる有田焼は、日本初の輸出磁器の一つであり、ヨーロッパにおける東アジアの陶磁器に対する認識の形成に貢献しました。
その特徴は次のとおりです。
- 白磁ベース
- コバルトブルーの釉下絵
- 後期には、多色の釉薬(赤絵や金襴手)が用いられるようになった。
歴史
1600年代初頭の起源
有田焼の歴史は、1616年頃、有田近郊で磁器の主要成分であるカオリンが発見されたことから始まります。この工芸は、朝鮮の陶工である李参平(別名:金ヶ江三兵衛)によってもたらされたと言われています。李参平は、文禄・慶長の役(1592~1598年)の際に強制移住させられた後、日本の磁器産業の創始者として知られています。
江戸時代:隆盛
17世紀半ばまでに、有田焼は国内外で高級品としての地位を確立しました。伊万里港を経由してオランダ東インド会社(VOC)によってヨーロッパに輸出され、中国の磁器と競合し、西洋の陶磁器に大きな影響を与えました。
明治時代と現代
有田の陶工たちは、明治時代に西洋の技術と様式を取り入れ、変化する市場に適応しました。今日でも、有田は伝統的な技法と現代の革新を融合させ、高級磁器生産の中心地であり続けています。
==有田焼の特徴==
材料
- 泉山採石場産カオリンクレー
- 約1300℃の高温で焼成
- 耐久性のあるガラス質磁器ボディ
装飾技法
| 技法 | 説明 |
|---|---|
| 染付(そめつけ) | 釉薬をかけて焼成する前にコバルトブルーで彩色します。 |
| 赤絵(あかえ) | 初焼成後に施される技法で、鮮やかな赤、緑、金などが含まれます。 |
| 金襴手(きんらんで) | 金箔と精巧な装飾が施されます。 |
モチーフとテーマ
代表的なデザインには以下が含まれます。
- 自然:牡丹、鶴、梅
- 民話と文学の場面
- 幾何学模様とアラベスク模様
- 中国風の風景画(輸出初期)
製造工程
1. 粘土の準備
カオリンは採掘され、粉砕され、精製されて、加工可能な磁器素地が作られます。
2. 成形
職人は、器の複雑さや形状に応じて、手ろくろや型を使って器を成形します。
3. 一次焼成(素焼き)
釉薬をかけずに乾燥させ、焼成して型を固めます。
4. 装飾
釉下彩は酸化コバルトで施されます。施釉後、二度目の高温焼成で磁器はガラス化されます。
5. 上絵付け(オプション)
多色バージョンの場合は、エナメル塗料を追加し、低温(約800℃)で再度焼成します。
文化的意義
有田焼は、芸術と産業としての日本の磁器の始まりを象徴しています。
経済産業省により「日本の伝統工芸品」に指定されました。
この工芸品は、日本の無形文化遺産の取り組みの一環としてユネスコに認定されています。
それは世界中の現代陶芸芸術や食器デザインに影響を与え続けています。
有田焼の今
現代の有田焼の芸術家たちは、何世紀も昔から伝わる技法とミニマリスト的な現代美学を融合させることが多い。
有田町では毎年春に「有田陶器市」が開催され、100万人を超える来場者が訪れます。
九州陶磁美術館や有田ポーセリンパークなどの博物館では、文化遺産を保存し、推進しています。