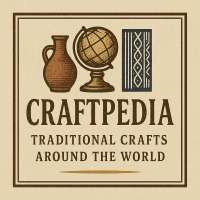Ko-Imari
Ko-Imari

古伊万里(古伊万里)は、主に17世紀に生産された、日本の伊万里焼の最も初期かつ象徴的な様式を指します。これらの磁器は有田町で作られ、近くの港町である伊万里から輸出されました。この港から古伊万里の名が付けられました。古伊万里は、そのダイナミックな装飾様式と、初期の世界的な磁器貿易における歴史的重要性で特に有名です。
歴史的背景
古伊万里焼は、江戸時代初期、1640年代頃、有田地方で磁器土が発見されたことをきっかけに誕生しました。当初は中国の青磁の影響を受けていましたが、地元の陶工たちは独自の様式を確立し始めました。明朝の崩壊により中国からの磁器輸出が減少すると、日本の磁器は特にオランダ東インド会社との貿易を通じて、国際市場の空白を埋めるようになりました。
主な特徴
古伊万里の特徴としては、次のようなものが挙げられます。
- 大胆で色彩豊かなデザイン。典型的にはコバルトブルーの下絵付けと、赤、緑、金の上絵付けのエナメルが組み合わされています。
- ほぼ全面を覆う緻密で対称的な装飾は、しばしば「華麗」あるいは「豪華絢爛」と評されます。
- 菊、牡丹、鳳凰、龍、様式化された波や雲などのモチーフが描かれています。
- 後世のより洗練された作品に比べて、磁器の厚みが厚い。
古伊万里焼は家庭用としてのみ作られたわけではありません。ヨーロッパ人の好みに合わせて仕立てられた作品も多く、大きな皿、花瓶、装飾用の器などもありました。
輸出とヨーロッパでの受容
古伊万里焼は17世紀から18世紀初頭にかけて大量に輸出され、ヨーロッパの上流階級の間で流行の高級品となりました。ヨーロッパ各地の宮殿や貴族の邸宅では、マントルピース、キャビネット、テーブルなどが古伊万里焼で飾られました。ヨーロッパの磁器メーカー、特にマイセンやシャンティイでは、古伊万里のデザインに着想を得た独自の磁器を製作し始めました。
進化と変遷
18世紀初頭には、伊万里焼の様式は進化を遂げ始めました。日本の陶工たちはより洗練された技法を開発し、鍋島焼のような、優雅さと抑制を重視した新しい様式が生まれました。現在、「古伊万里」という用語は、これらの初期の輸出作品を、後世の国内産や復興作品と明確に区別するために使用されています。
レガシー
古伊万里は、世界中のコレクターや美術館から高い評価を受け続けています。古伊万里は、日本の陶芸が世界的に発展した初期の象徴であり、江戸時代の職人技が光る傑作とされています。古伊万里の鮮やかなデザインと卓越した技術は、伝統陶芸家だけでなく現代陶芸家にもインスピレーションを与え続けています。
==伊万里焼との関係==
古伊万里焼はすべて広義の伊万里焼に属しますが、すべての伊万里焼が古伊万里と呼ばれるわけではありません。古伊万里焼と古伊万里焼の区別は、主に時代、様式、そして用途によって行われます。古伊万里焼とは、特に初期の時代を指し、その躍動感、輸出志向、そして豊かな装飾が施された表面が特徴です。