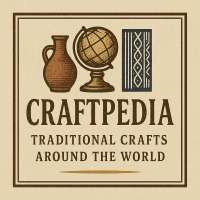備前焼
⚠️ This page has not yet been translated into Armenian.
備前焼(びぜんやき)は、現在の岡山県にあたる備前国を起源とする日本の伝統的な陶器です。日本最古の陶器の一つで、独特の赤褐色、釉薬を施さない素朴で素朴な風合いが特徴です。
備前焼は国の重要無形文化財に指定されており、備前窯は日本六古窯の一つに数えられています。
概要
備前焼の特徴は以下のとおりです。
- 伊部産の良質な粘土を使用
- 釉薬をかけずに焼成する「焼き締め」技法
- 伝統的な穴窯または登り窯で、薪を使って長時間じっくりと焼成
- 火、灰、そして窯の中での焼成によって生まれる自然な模様
備前焼は、施された装飾ではなく、窯による自然な焼き上がりによって最終的な美しさが決まることから、それぞれの作品がユニークであると考えられています。
歴史
起源
備前焼の起源は、少なくとも平安時代(794~1185年)にまで遡り、その起源は素焼きの初期の形態である須恵器にあります。鎌倉時代(1185~1333年)には、備前焼は堅牢な実用陶器を特徴とする独特の様式へと発展しました。
封建時代の保護
室町時代(1336~1573年)と江戸時代(1603~1868年)には、備前焼は池田氏や地方の大名の保護の下、栄えました。茶道、台所用品、そして宗教的な用途に広く用いられました。
衰退と復興
明治時代(1868~1912年)には産業化が進み、需要は衰退しました。しかし、備前焼は20世紀に入り、後に人間国宝に認定される金重陶陽をはじめとする名陶師たちの尽力によって復興を遂げました。
土と素材
備前焼は、備前焼とその周辺地域で採れる鉄分を多く含む土(ひよせ)を使用します。この土の特徴は、
- 数年間熟成させることで、可塑性と強度を高めていること
- 焼成後も展延性がありながらも耐久性があること
- 灰や炎に強く反応するため、自然な装飾効果が得られることです
窯と焼成技術
伝統的な窯
備前焼は、主に以下の窯で焼かれます。
- 穴窯:斜面に築かれた単室のトンネル型窯
- 登窯:斜面に築かれた多室の階段型窯
焼成工程
- 薪焼きは10~14日間連続して行われます。
- 温度は最高1,300℃(2,370℉)に達します。
- 松材の灰が溶けて表面に溶け込みます。
- 釉薬は使用せず、窯の作用のみで表面仕上げが行われます。
美的特徴
備前焼の最終的な外観は、以下の要素によって決まります。
- 窯内の位置(正面、側面、燃えさしに埋まる)
- 灰の堆積と炎の流れ
- 使用する木材の種類(通常は松)
一般的な表面パターン
| 模様 | 説明 |
|---|---|
| 胡麻 (ゴマ) | 溶けた松灰によって生じたゴマのような斑点 |
| 緋襷 (ヒダスキ) | 作品に稲わらを巻き付けることで生じた赤褐色の線 |
| 牡丹餅 (ボタモチ) | 灰を遮るために表面に小さな円盤を置いたことで生じた円形の跡 |
| 窯変 (窯変) | 炎によって生じるランダムな色の変化と効果 |
形態と用途
備前焼には、機能的なものから儀式的なものまで、幅広い種類があります。
機能ウェア
・水指(みずさし) ・茶わん ・花器(ハネレ) ※徳利・ぐい呑(徳利・ぐい呑)
- 乳鉢と保存瓶
芸術および儀式での使用
- 盆栽鉢
- 彫刻作品
- 生け花用花瓶
- 茶道具
文化的意義
- 備前焼は、不完全さと自然の美しさを重んじる「侘び寂び」の美意識と深く結びついています。
- 茶人、生け花、陶磁器収集家の間で今もなお愛されています。
- 多くの備前焼作家が、何世紀にもわたって受け継がれてきた技法を用いて、今もなお作品を制作し続けています。
著名な窯跡
- 伊部町:備前焼の伝統的な中心地。陶芸祭が開催され、多くの窯が稼働しています。
- 旧伊部学校(備前焼伝統現代美術館)
- 金重陶陽窯:教育目的で保存されています
現代の実践
今日、備前焼は伝統的な陶工と現代の陶工の両方によって生産されています。古来の技法を継承する陶工もいれば、形や機能性を実験的に追求する陶工もいます。この地域では毎年秋に「備前焼まつり」が開催され、何千人もの来場者やコレクターが訪れます。
著名な備前焼作家
- 金重陶陽 (1896–1967) – 人間国宝
- 山本陶山
- 藤原啓 – 人間国宝
- 隠崎龍一 – 現代の革新者